第八章新生
「函館市新川町二七四番地、及 上磯郡上磯町大字上磯村字飯生町百三十九番地の壱の一支店ヲ廃止ス。
無限責任社員、河村定一ハ大正十四年一月六日出資額ニ、金五萬円増加シテ出資額ヲ金十六萬円ト変更ス」
大正十四年、新川町支店の店長、鈴木繁延が退社したことにより、店を閉鎖したのである。上磯支店所在地は、先代、織右工門の住居でもあったが、大正十三年、正式に、引退した ことにより、上磯支店を整理し、函館市谷地頭町に別宅を構え、悠悠自適の生活にはいったのである。
二店を閉鎖したが、コドモ印製綿所は隆々として発展し続けていた。大正十二年には、小樽稲穂町大通りに小樽支店を設置し、小樽、札幌を商圏とし、この設置を機に、卸売の伸びは、予想を遥かに上回り、支店開設の意義は十二分に達成されつつあった。更に、大阪に「連絡所」を設置し、綿花の仕入れの取次、相場報告等の情報の収集に当たらせた。
「将来、必ず人口が急増するところ・・・」
これが定一、源二郎の考えていた支店設置の条件であった。小樽は開拓当初より、北海道進出と発展の根拠地であり、函館よりも発展していた地方であり、支店設置は、遅すぎた位であったが、当時、未だ、綿、蒲団の進出は初期の段階であり、取引の前途は有望であった。定一、源二郎は全道を視野に入れていたのである。大阪の「連絡所」は源二郎の東京経験が役に立った。商地としての大阪の重要性を源二郎は、先代にも定一にも、たびたび進言していたのである。
一方、本社の工場には判綿機十一台、夜具綿機十二台、打直し機七台が運転され、毎日千貫の製綿が仕上げられると共に蚊帳百帳が生産されていた。「物価がやや下落の兆候をみせはじめた大正末期、製綿業界は争って一せいに機械の増設に着手したのであった。この時、新たに購入した機械の不備ということもあり、最大需要期に予期したような成果をあげ得なかったという不運な一時期もあったが、当社はこの間を機械整備のために充分に活用した。その後、生産過剰で、同業者間に熾烈な競争が出現したときも、品質と数量をもって、堂々とこれに対抗し得る状態を備えていたのである。……機械の改良・増設に関してなおつけ加えておきたいことは、新しく購入したものを、より進歩的に改良するということの外に、河村製ともいうべき全く新しい独自なものを考案、試作したり、或は、機械と機械を連繋することによってセットものとしたり、木製のものをすっかり鉄製に作り直す等、あらゆる研究努力が払われたことである。 大正末期においては、使用動力約百馬力(予備電力を含む)、各種機械台数八十台を越えるにいたった。」と70年回顧録に記されている。
鶴岡町河村蒲団店では、しばしば特売会を開催し、函館の人気を一身に集めていた。綿、蒲団の需要は景気停滞の時代であったが衰えることはなかった。綿、蒲団は未来の商品であり限度は無かった。蒲団、綿、蚊帳といえば河村蒲団店であった。 商品として、ナフトルー尺十銭、友仙モスー尺二十三銭、上等友仙モスー尺二十九銭、上等モスー尺二十五銭、木綿夜具縞一反一円三十五銭、防寒真綿チョッキ一枚一円二十銭などが目玉商品であり、広告には、
 |
| 大正14年の源二郎 前列右から二人目 |
「わたも夜具縞も大暴落の底に達しました。今が絶好のお仕度時で御座います。」とある。
特売日には源二郎が先頭に立った。
特売日に買いに来る結婚間近の客を選んでは目玉商品とは別に、上質蒲団を販売した。金額が張り利益も大きかった。蒲団の色柄から値段まで損得をこえて親身に相談に乗った。商談が整うと、その紹介者まで謝礼し、季節の挨拶も欠かさなかった。その気配りは源二郎の商才によるものであり、社員教育も徹底していた。河村の蒲団の評価は上々であった。 河村全社の社員数は二百名に達していた。販売地域を全道、樺太、青森に拡げ、満州方面への輸出、上海からの原料の輸入も計画中で、いやが上にも発展し続けている大正十四年であった。
源二郎は、この年、将来を見越して、函館市青柳町二十三番地に居住する竹内クニより函館市五稜郭五十番地の土地百三十六坪を借受けるのである。幕末戦争の五稜郭が近かい土地であった。
即、買入れなかった理由は判然としない。一応、地代を支払い、その後、家を建築するまでの十数年は、畑として活用していたが、この土地に、源二郎と、とよは、一本の欅の苗を植えるのである。二人の記念樹であった。この樹が、北海道の激しい風雪に耐え、四十余年の長年月を成長し続けるのである。源二郎は、後年、成長し続けた喬木に己の事業の歴史と、哲学を見、昭和四十二年に発行された社内報、第二十二号に、「喬木」と題し、次のように書いた。
「これは、木自身の持つ強い生命力によって、懸命に根を張り、枝を繁らせ、幹を太らせた結果ですが、然し、それのみではありません。他からの恵みに負うところが多いのです。暖かい日光、豊かな水、清らかな空気等の限りない恩恵によるところが大であります。それ故にこそ、みじろぎもしない喬木となり得たのであります。企業の繁栄の姿もこの喬木と同じではないでしょうか。」
その時の源二郎は己の将来の成長を、この一本の欅の苗に託そうとしていたのかもしれなかった。
大正十四年五月、大正天皇の「ご成婚二十五周年(銀婚式)」の祝典が行われ、全国が、その奉祝ムードに包まれた。
また、その年が終わりに近づいた十二月六日には皇太子殿下(昭和天皇)の第一子、内親王(照宮成子内親王)が誕生し、国民待望の親王の誕生ということで、全国は慶びで沸き返ったのである。その一年後、大正天皇が崩御するのであるが:… 一方ヽ日本の資本主義は、大戦中に中国への侵略を進めて権益を拡大することで帝国主義国としての発展を遂げていた。しかし国内市場は相変わらず狭く、日本経済は海外貿易に強く依存しなければならず、しかも大戦中とは打って変わった欧米諸国との激しい競争に直面していた。
輸出産業の中心は、依然として紡績業を主体とした軽工業で、大戦下に発展をはじめた重化学工業は、欧米諸国に対抗出来ずに伸び悩んでいた。機械等の重工業製品は、英米などから不利な条件で輸入せざるを得なかった。多面、多数の中小企業が、おくれた農村を母胎として極度に低い賃金を武器に存続していたが、その多くは中国市場むけであった。この不利な条件を補うために日本は中国に対して不平等条約にたよって、略奪的な貿易や資本輸出をすすめていった。つまり日本帝国主義は、経済的に英米に従属しつつ中国を支配下におこうとする二面性をもち、しかも後者の部面では英米とも競り合うという関係にあったのである。
一方、経済においては原内閣以来著しく膨張した財政に、更に、震災復旧費が加わったため、公債財源に大幅に依存して、やっとバランスをとって来たが新規公債の発行も行き詰まっていた。戦後恐慌以来、独占資本が強化され、産業の合理化が課題となった時期においては従来のような放漫財政は財界には堪えられなくなっていた。行財政整理によって財政の基礎を固め、物価の安定をはかって、輸出競争力を強めることは財界の強い要望であった。
そのため浜口雄幸蔵相は内閣成立後から緊縮財政の方針を打ち出し、国民に消費節約を訴えていたが、大正十四年度の予算編成を前に行財政の整理が進められていた。大正十四年三月二十九日、第五十議会で、久しく国民が待望していた普通選挙法案が成立した。普選法の成立は、日本の議会史上、画期的なものであった。
大正年間は日本にとって、激動に次ぐ激動の時代であったが、この後も辛苦の時代が続いて行くのである。
大正十五年一月一日、内閣総理大臣、加藤高明は、「光明と努力の新年」と題して年頭所感を発表したが、主旨は次ぎのようなものであった。 「御生誕遊ばされた皇孫殿下の御肥立ちを第一に慶び、次に、欧州列国が漸く安定の域に達すると共に、隣邦支那が経済的に発達の質を示し、国体の統一を平和の裡に成し遂げつつあること。日本国内に於いては、関東大震災の打撃により、財界が極度の不安に陥ち入っていたが、政府、国民が整理緊縮に努め、前途に一転の光明を見出しつつあること・・併し、今日、之によって、決して油断してはならぬ。今日迄緊縮せる努力を将来も持続してゆかねばならぬ。」
と結び、国民に対して緊縮政治を強く訴えたのだが、当の本人は、第五十一議会が再開された二日目の大正十五年一月二十二日、貴族院の議場で倒れ、二十八日に死去するのである。
代わって、一月三十日、若槻内相が、憲政会総裁を継ぎ、首相となった。
若槻内閣が成立すると、憲政会、政友会、政友本党の三派鼎立となり、政局は再び不安定になり政党間の泥試合となって行く。疑獄事件や摂政への大逆事件なども起こり、「梅雨が晴れて、かすかながらも日光を望むを得た」ようにみえたのもほんのつかの間、再び政界に暗雲が漂い始めるのである。また既成の秩序が行きづまり、さらには解体の方向に向っているという意識は左翼ばかsSでなく、右翼の一部や、文壇の間にも広がり始めていた。これらから、労農運動が激しい盛り上がりをみせ天皇制権力と帝国主義体制との全面的変革を目指すマルクス主義が鋭い影響力を持ち始めるのに対して、権力者の方では、力によって既成秩序を守ろうとする姿勢を強めていく。折から支那では民族解放闘争と帝国主義諸国との間に激突が始まろうとしていた。戦争と、ファシズムの時代への突入であった。
その頃、函館は函館としての産業立市の自治化が叫ばれていた。
源二郎は昭和元年から数えて十一年後、漸く独立の旗を掲げるのであるが、その時まで奉公一筋。会社の重鎮として、家を守る妻とよと共に、志高く、闘志をたぎらせ、懸命にこの時を疾走して行くのである。
大正天皇の大喪儀は、昭和二年二月二十七日、新宿御苑で行われる事が決定していた。
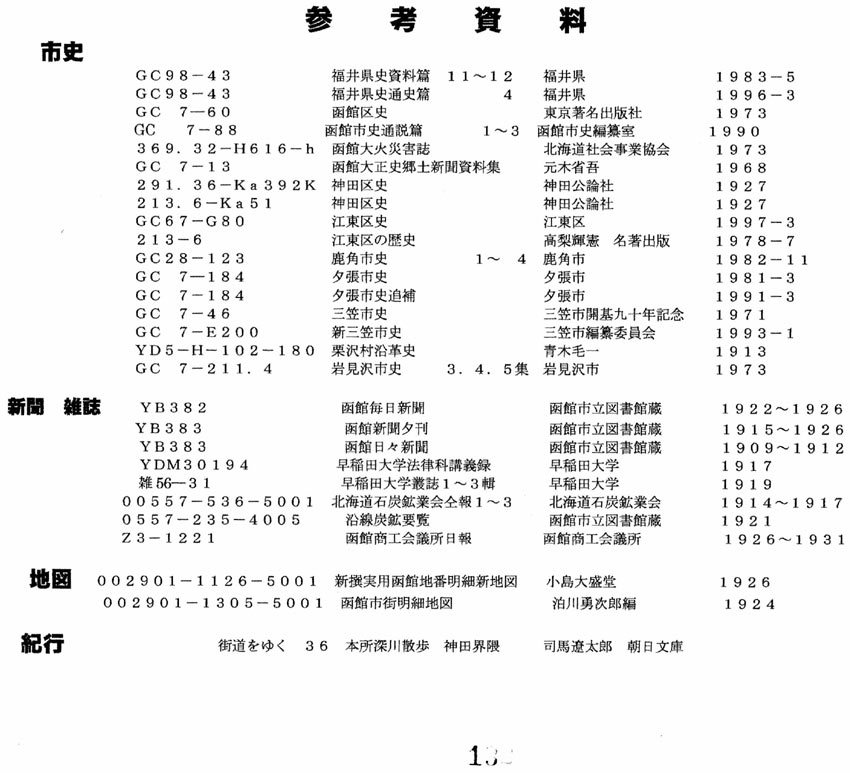
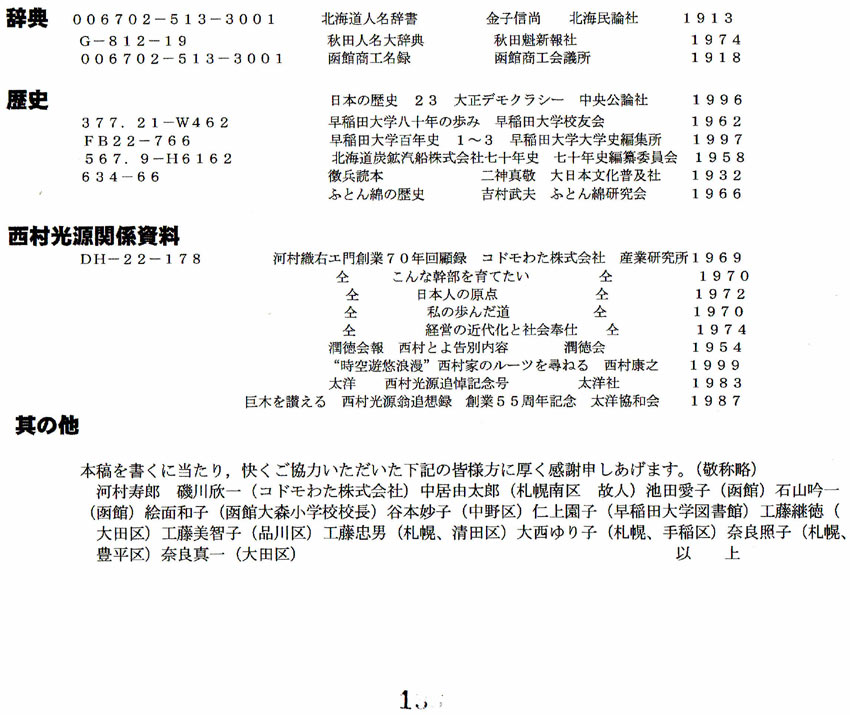
|
|
|